介護施設を利用するとき、思った以上に家計を圧迫するのが 食費と居住費 です。介護保険がカバーするのは介護サービス費用の一部であり、食事代や部屋代は原則自己負担となります。
そんなときに役立つのが 「負担限度額認定証」 です。これを取得すれば、食費・居住費の負担が大幅に軽減される可能性があります。
負担限度額認定証とは?
- 介護保険施設(特養・老健・療養型病床など)やショートステイを利用する際に、食費・居住費の自己負担を軽減できる制度です。
- 本人の 所得 や 資産(預貯金など) に応じて区分が決められ、食費・居住費の上限額が設定されます。
- 制度上は「介護保険負担限度額認定証」と呼ばれ、市区町村から交付されます。
対象になる人
以下の条件を満たす人が対象となります。
- 世帯の所得が一定以下例:住民税非課税世帯など
- 資産が一定以下
- 単身の場合:1,000万円以下
- 配偶者がいる場合:2,000万円以下
申請の流れ
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① 申請書の入手 | 市区町村役場の介護保険担当課で入手 | HPからダウンロード可能な自治体もあり |
| ② 必要書類を準備 | 介護保険証、通帳写し、年金通知書など | 配偶者分も必要な場合あり |
| ③ 申請 | 市区町村窓口へ提出(郵送可の場合もある) | 不備があると差し戻されるので要注意 |
| ④ 判定・交付 | 所得・資産を確認後、認定証が交付 | 審査に2~4週間かかるケースも |
必要書類
申請時には以下の書類が必要です。
- 介護保険被保険者証
- 本人および配偶者の 預貯金通帳の写し
- 年金額がわかる書類(年金通知書・年金振込通知など)
- 印鑑(認印で可)
- マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書
注意点と申請のコツ
- 資産確認が厳格化預貯金の通帳コピーの提出が必須。金融機関によっては残高証明書を求められる場合もあります。
- 配偶者の資産も対象同居・別居にかかわらず、配偶者の預貯金も確認対象になります。
- 有効期限は1年間原則1年ごとの更新が必要。期限切れに気づかず「自己負担が増えた」というケースも多いため、更新は早めに行いましょう。
- 施設に提出する必要あり認定証は交付されたら、必ず利用施設に提示しなければ軽減措置が適用されません。
まとめ
- 「負担限度額認定証」を取得すれば、食費・居住費が数万円単位で軽減される可能性があります。
- 所得・資産の条件を満たすかどうかがポイントで、書類の準備には手間がかかりますが、経済的負担を減らす大切な制度です。
- 早めに申請して、余裕をもって制度を活用しましょう。
👉 関連記事
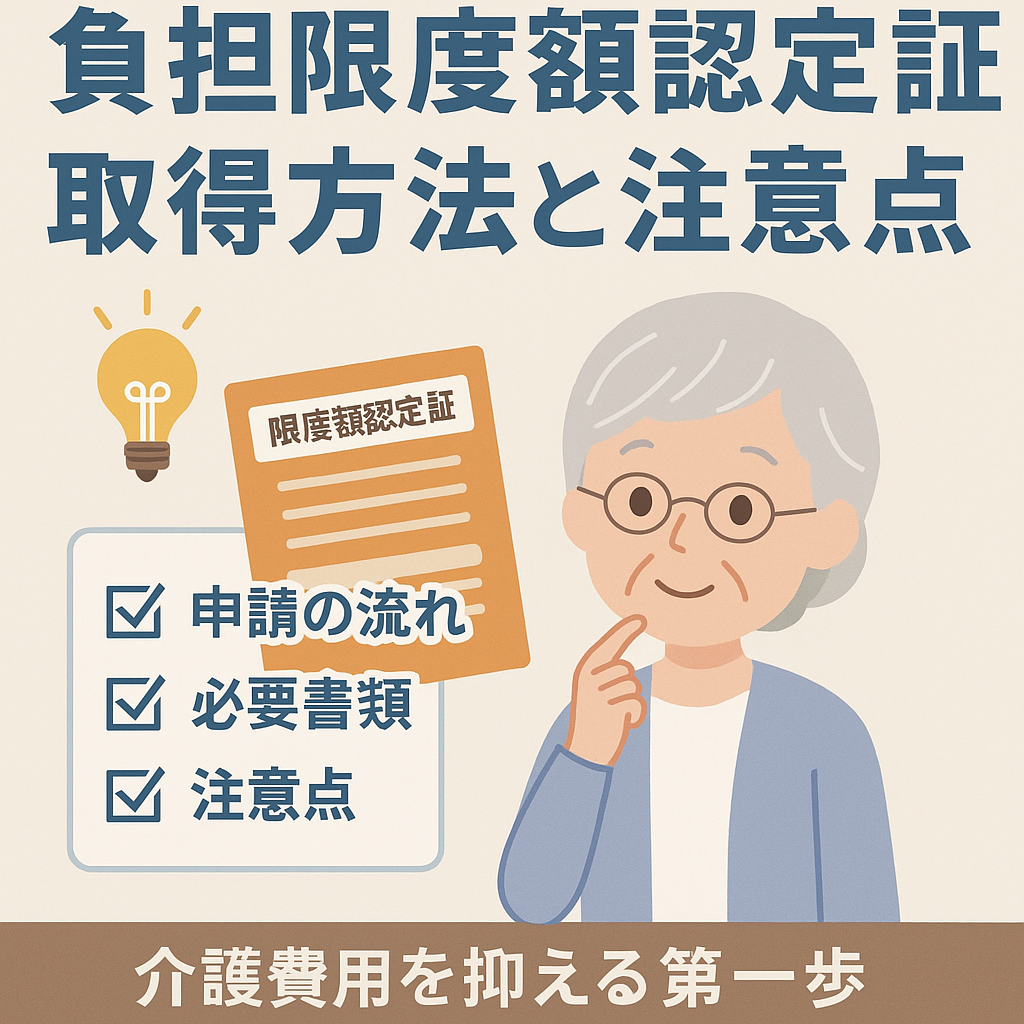
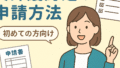
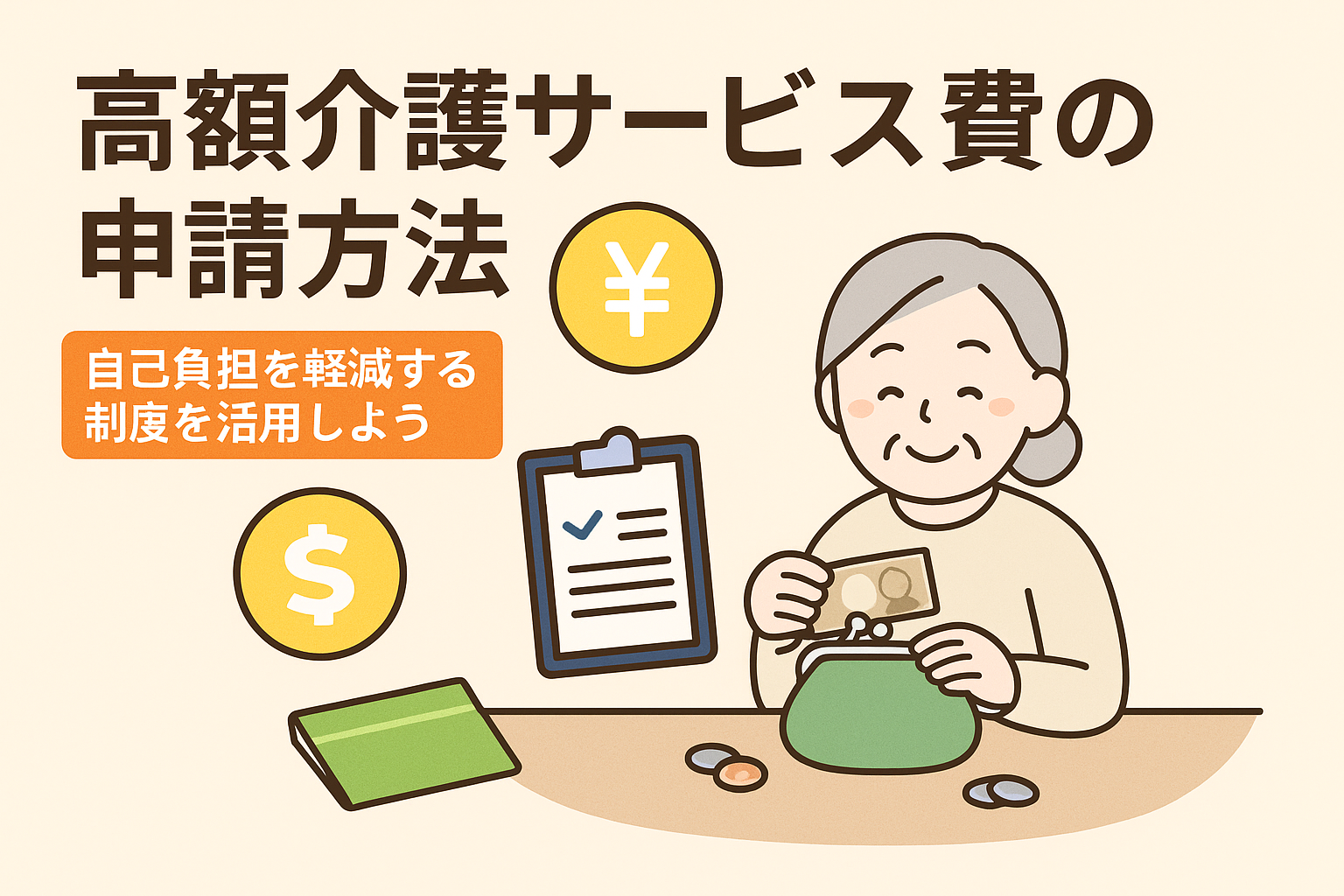
コメント