Q1. 主治医にはどんなことを相談すればいいですか?
主治医は、病気の診断や薬の処方をしてくれる一番の相談先です。
- 日々の体調変化(例:食欲の低下、咳の増加)
- 薬の副作用や飲み合わせの不安
- 今後の治療方針や介護への影響
短い診察時間でも、あらかじめメモして伝えるとスムーズです。
Q2. 主治医との診察を有意義にするコツは?
- 気になる症状を「時系列」で整理しておく
- 質問リストを事前に作っておく
- ケアマネジャーに同席してもらう
これにより、聞き漏れや伝え忘れを防ぎ、介護と医療の連携が取りやすくなります。
Q3. 訪問看護では何をしてくれるの?
訪問看護師は自宅に来て、次のような支援をしてくれます。
- 薬の管理や体調チェック
- 床ずれや創傷のケア
- リハビリ補助
- 入浴や清拭の介助
家族が不安に思う小さなことでも気軽に相談できます。
Q4. 訪問看護を利用するメリットは?
- 介護者だけでは難しい医療的ケアを任せられる
- 夜間や休日の緊急時対応について安心できる
- 家族の負担や介護疲れが軽減される
介護者が「自分一人で抱え込まなくていい」と思えることが最大のメリットです。
Q5. 医療と介護をつなぐ存在は誰ですか?
- ケアマネジャー:医師・看護師・介護職の間で情報を整理し、連携を支援
- 地域包括支援センター:医療・介護・福祉のネットワークをつなげてサポート
- サービス担当者会議:医療・介護の多職種が集まり、利用者の状態やケア方針を共有
これらを活用すると、介護と医療の「チーム連携」が強化されます。
Q6. 家族はどう関わればよいですか?
- 体調や生活の様子を日々記録し、主治医や訪問看護に共有
- 不安や疑問は遠慮せず相談する
- 介護者自身の体調や気持ちも含めて伝える
「医療チームと一緒に介護している」という意識を持つことが大切です。
まとめ
- 主治医には「症状の変化と質問」をしっかり伝える
- 訪問看護は日常のケアと家族の安心をサポートしてくれる
- ケアマネジャーや地域包括支援センターが医療と介護をつなぐ橋渡し役
- 医療と介護のチームを上手に活用することで、在宅介護の負担が軽減される
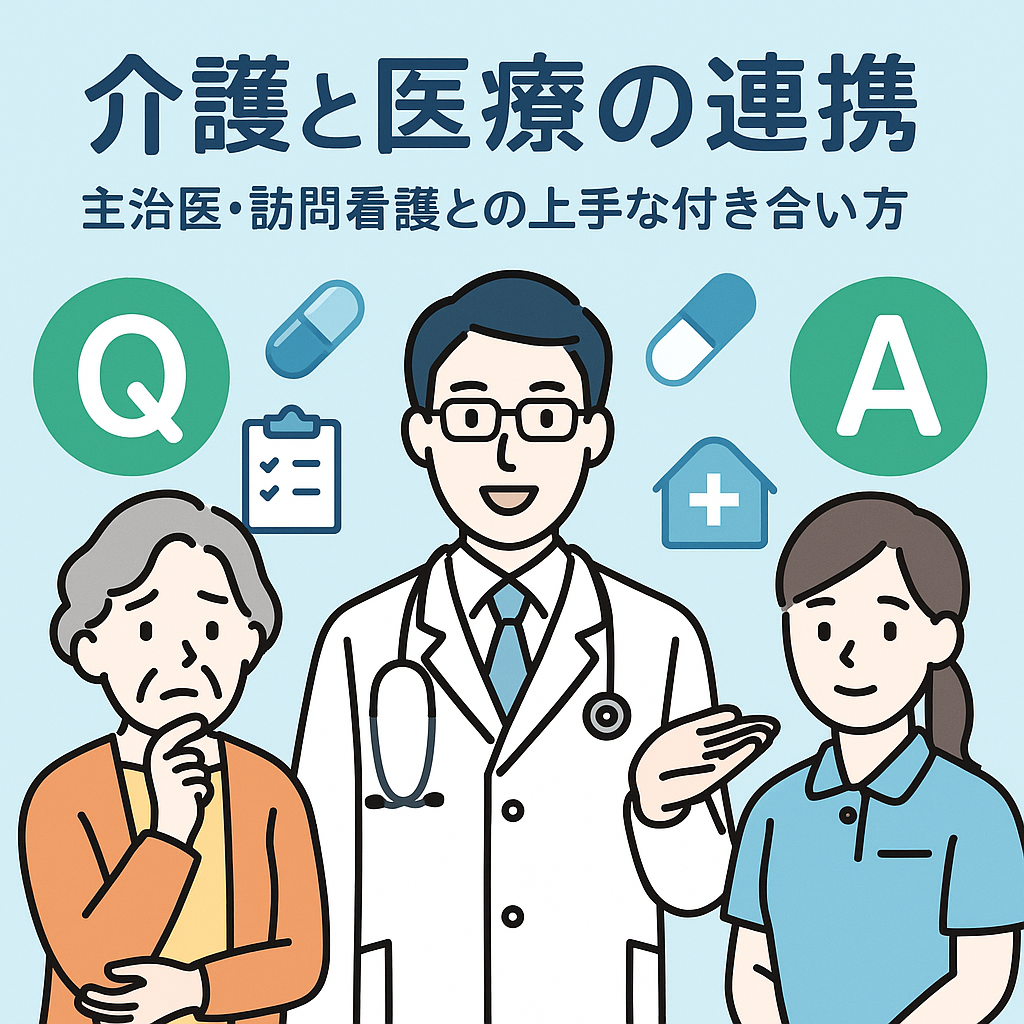

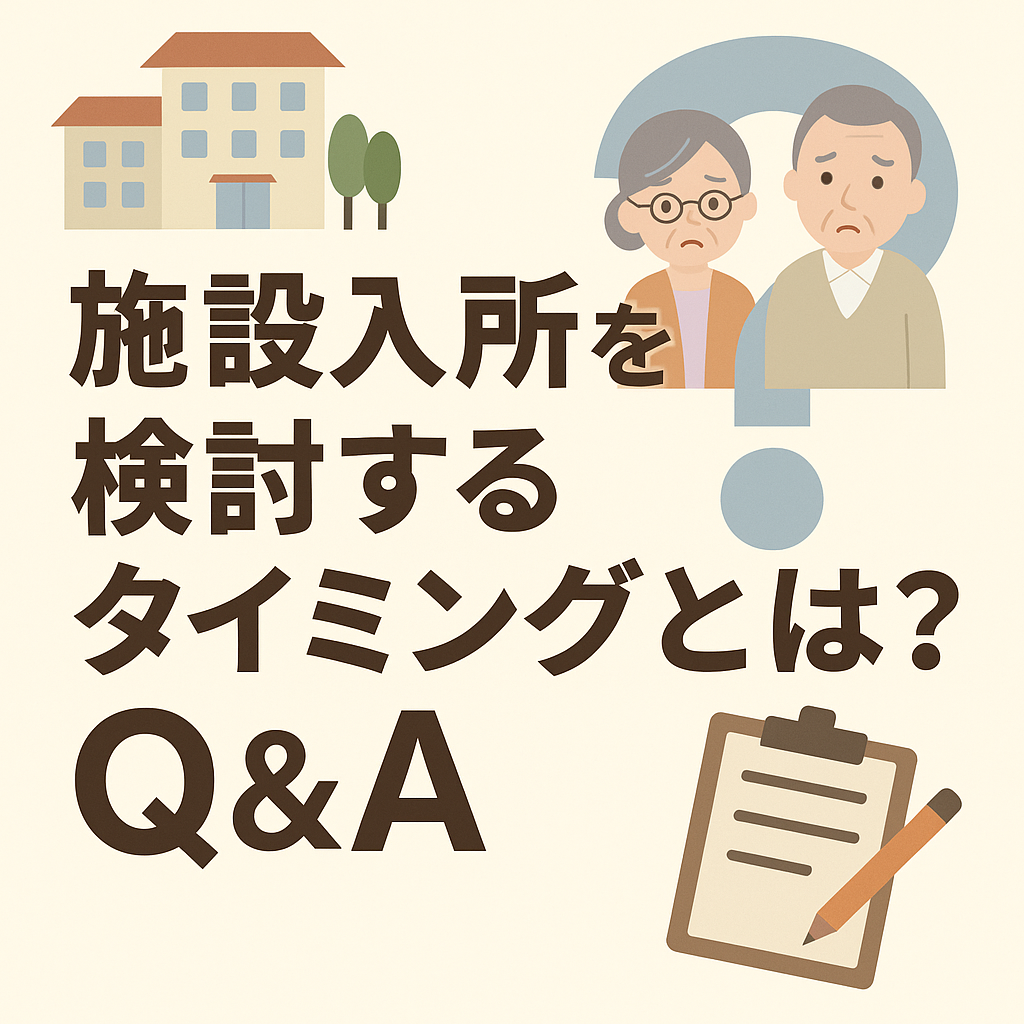
コメント