はじめに
介護サービスは一度利用を始めたらずっと続けなければならないと思われがちですが、実際には 途中でやめるケース も少なくありません。体調の変化や費用の問題、本人や家族の希望など理由はさまざまです。
大切なのは「やめた後どうするか」を考えること。本記事では、実際の事例を交えながら、サービスをやめた後に活用できる支援について解説します。
事例紹介:デイサービスをやめた80代女性のケース
80代の女性Aさんは、要介護2で週2回デイサービスを利用していました。家族としては「安心して外出できるし、リハビリにもなる」と思っていましたが、Aさん本人は次第に「もっと自宅で自由に過ごしたい」という気持ちを強めていきました。
加えて、利用料や送迎の手間など、家族にも負担感が出てきました。そこでケアマネジャーに相談し、デイサービスを一旦中止することになりました。
しかし完全にサービスをやめてみると、今度は「一人で過ごす時間が長くなり心配」「買い物や家事の一部が大変」といった新たな不安が出てきました。
そこで地域包括支援センターに相談した結果、次のような支援を利用することにしました。
- 配食サービスを導入し、安否確認も兼ねて栄養面をサポート
- シルバー人材センターに依頼して庭の手入れをお願い
- 民間の見守りサービスを活用し、家族が離れていてもスマホで安否確認
こうした工夫により、本人の希望を尊重しながら安心して在宅生活を続けることができました。
サービスをやめた後に使える支援
1. 地域包括支援センター
介護サービスをやめても、まず相談先となるのが地域包括支援センターです。必要に応じて民間サービスや地域資源を紹介してもらえます。
2. 自治体の生活支援サービス
市区町村によっては、ゴミ出し支援・安否確認・移動支援といった 介護保険外サービス を実施している場合があります。
3. 民間サービスの活用
- 配食サービス:食事を届けながら安否確認
- 訪問理美容:自宅で散髪やカラーリング
- 見守り機器:センサーやカメラで安否を家族に通知
4. 地域のボランティアやサロン
高齢者向けの交流の場やボランティアによる支援を利用することで、孤独感の解消や軽い支援を受けられます。
サービスをやめる際の注意点
- ケアマネに必ず相談する やめる前にケアマネジャーに相談し、代わりにどんな支援が必要か整理しましょう。
- 再開には時間がかかることも 一度やめたサービスを再開する場合、手続きや空き状況によって時間がかかることがあります。
- 「完全にやめる」のではなく「一部減らす」方法もある 例えば「週2回のデイサービスを週1回にする」など、柔軟に調整できることも多いです。
まとめ
介護サービスを途中でやめること自体は珍しいことではありません。大切なのは「やめることで生まれる不安や負担をどう補うか」です。
- ケアマネや地域包括支援センターに相談する
- 公的サービスと民間サービスを組み合わせる
- 家族の希望と本人の希望のバランスをとる
これらを意識すれば、本人の生活の質を守りながら、家族の負担も軽減できます。
介護サービスは「使うか、やめるか」の二択ではなく、その時々の状況に合わせて柔軟に選択するもの です。
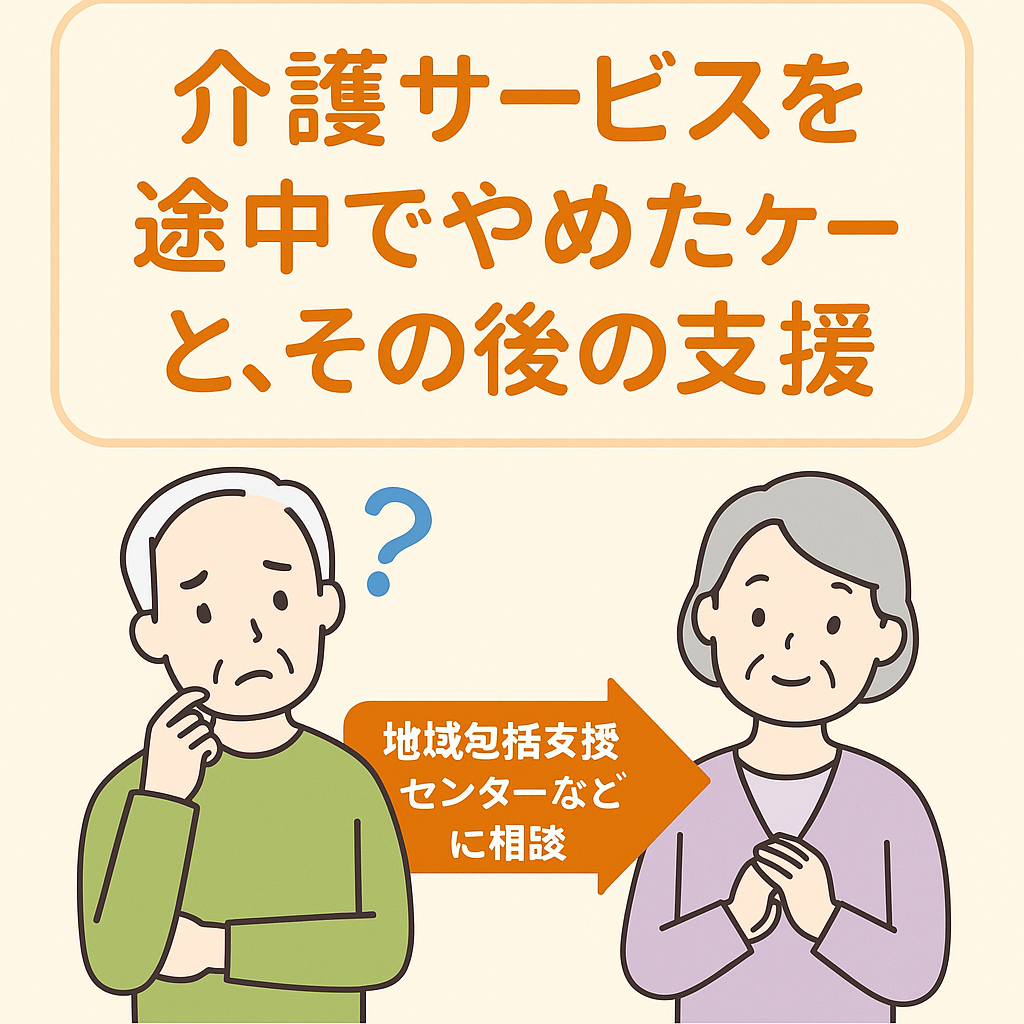
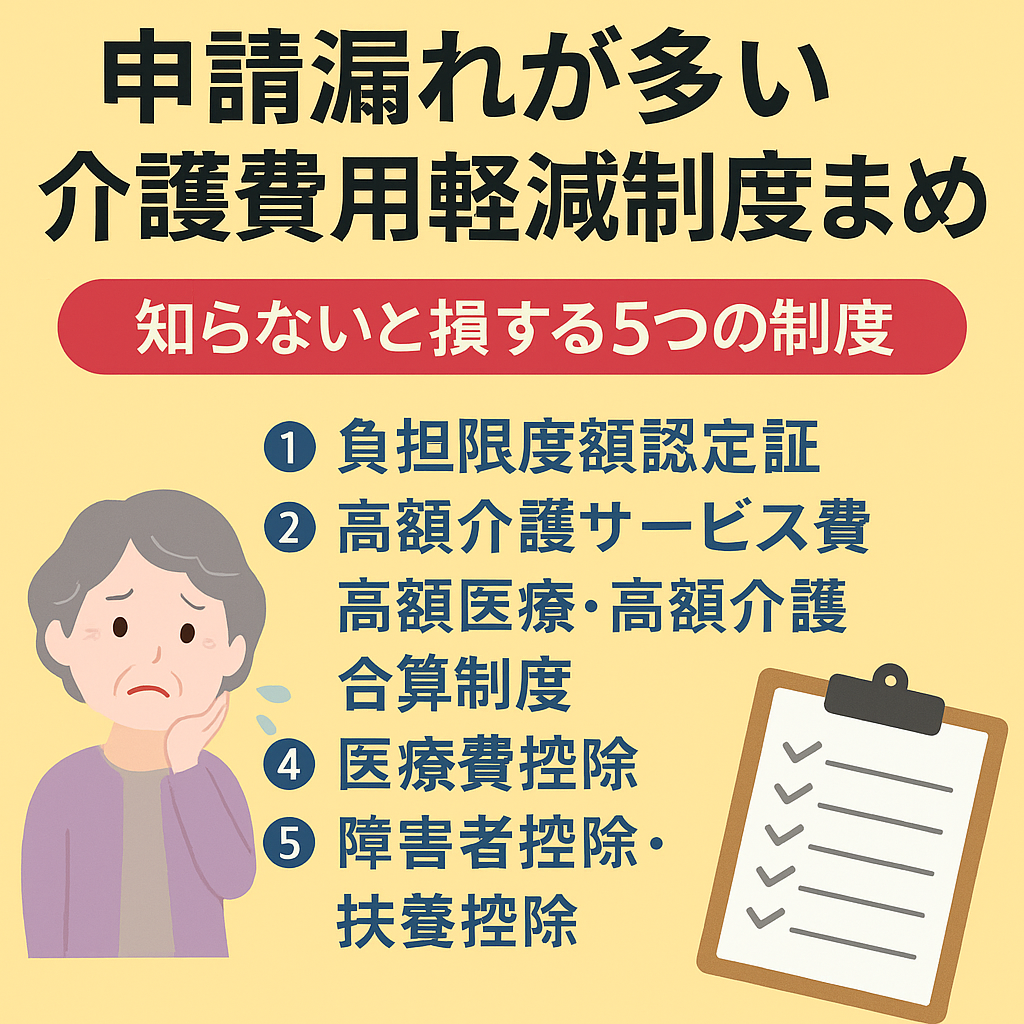

コメント