在宅での介護は、家族の協力なしには成り立ちません。介護は突発的に始まることもあれば、長期にわたって続くこともあります。そのため、最初の段階で「誰が何をどこまで担うのか」を家族で話し合っておくことが非常に大切です。ここでは、在宅介護を無理なく続けるために家族で確認しておきたいポイントをまとめます。
1. 介護の役割分担を明確にする
介護は「ひとりが抱え込む」ことが最も大きな負担になります。
- 誰がメインで介護を担うか
- 通院の付き添いは誰が担当するか
- 買い物や食事の準備、金銭管理をどう分けるか
こうした日常の役割分担を最初に話し合っておくことで、後から不満やトラブルになるのを防ぐことができます。ポイントは「できること」と「できないこと」を率直に伝え合うことです。
2. 介護費用の分担と管理
在宅介護では、公的制度でカバーできる部分もありますが、それでも自己負担は発生します。
- サービス利用料や食費・光熱費
- 介護用品(オムツや福祉用具)の費用
- 通院や送迎にかかる交通費
これらを誰がどのように負担するのかを決めておくことが重要です。特に兄弟姉妹が複数いる場合、「特定の人だけが費用を負担している」という不公平感が大きな不満につながることがあります。預金や年金の使い方、介護保険サービスの利用状況を家族全員で共有しておくと安心です。
3. 介護サービスの利用について
「家族だけで介護を続ける」のは大きな負担になります。
デイサービス、ショートステイ、訪問介護などを積極的に活用することで、介護者の休息や就労の継続が可能になります。
ケアマネジャーを交えて話し合うことで、介護保険サービスをどう組み合わせるか、どの程度利用するかを具体的に整理できます。大切なのは「無理をしない」「在宅だけで抱え込まない」ことです。
4. 将来的な方針を決めておく
在宅介護はいつまで続けるのか、どのような状況になったら施設入所を検討するのかといった「将来の方針」を話し合っておくことも欠かせません。
- 要介護度が重くなった場合の対応
- 介護者が体調を崩したときのバックアップ体制
- 緊急入院など突発的な出来事が起きたときの連絡・対応方法
こうしたシナリオを想定しておくことで、いざという時に慌てず行動できます。
5. 定期的に家族会議を開く
介護は始めた時点の想定通りには進みません。介護者や本人の状態が変化すれば、役割や費用の負担も変わってきます。そのため、定期的に「家族会議」を開き、現状の負担や不満を共有していくことが大切です。
特に「疲れている」「つらい」といった気持ちを安心して話せる場を作ることで、介護うつや孤立を防ぐことにつながります。
まとめ
在宅介護を続けるには、家族全員が同じ方向を向き、協力体制を作ることが欠かせません。
- 役割分担
- 費用負担
- サービス利用の方針
- 将来の見通し
- 定期的な見直し
これらをきちんと話し合っておくことで、介護を「無理なく」「長く」続けることができます。介護は一人で抱え込むものではなく、家族みんなで支えるもの。合意形成を積み重ねることで、介護する人もされる人も安心できる在宅生活を実現できます。

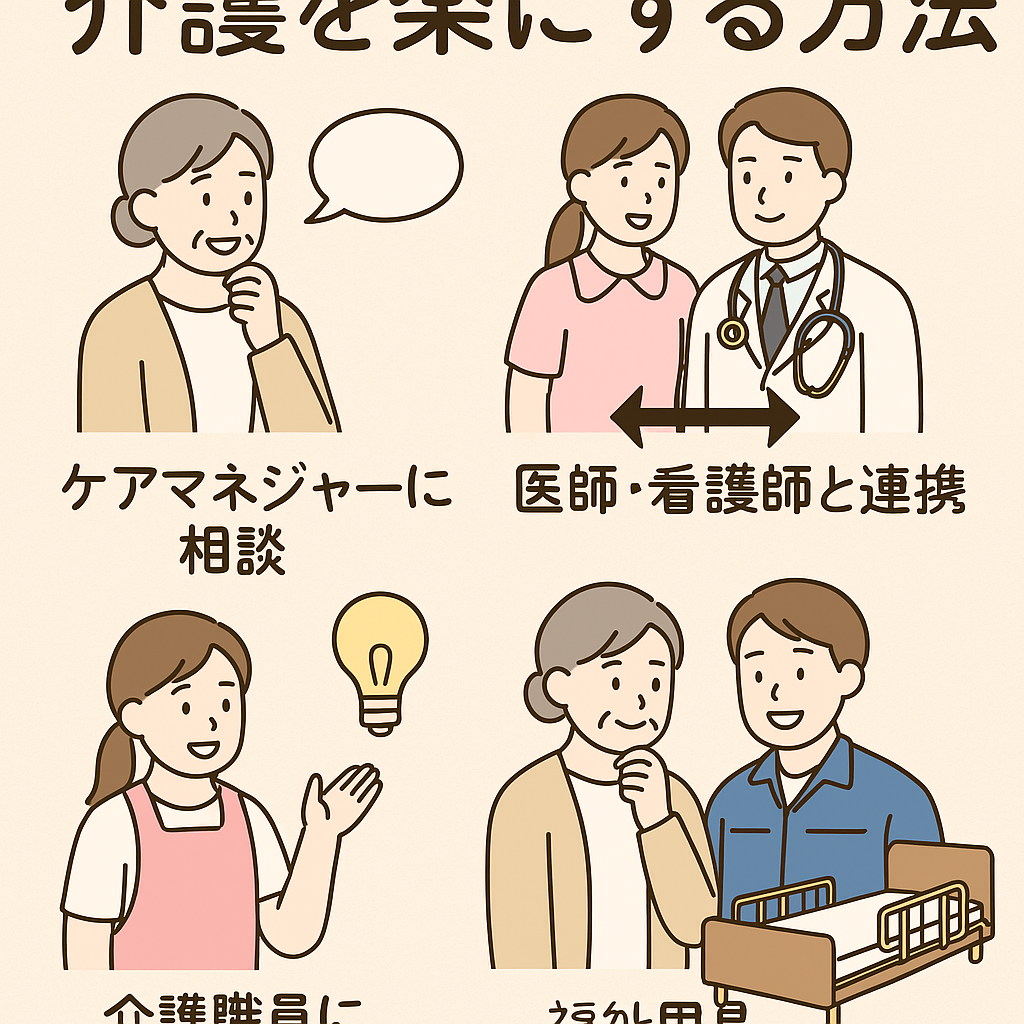
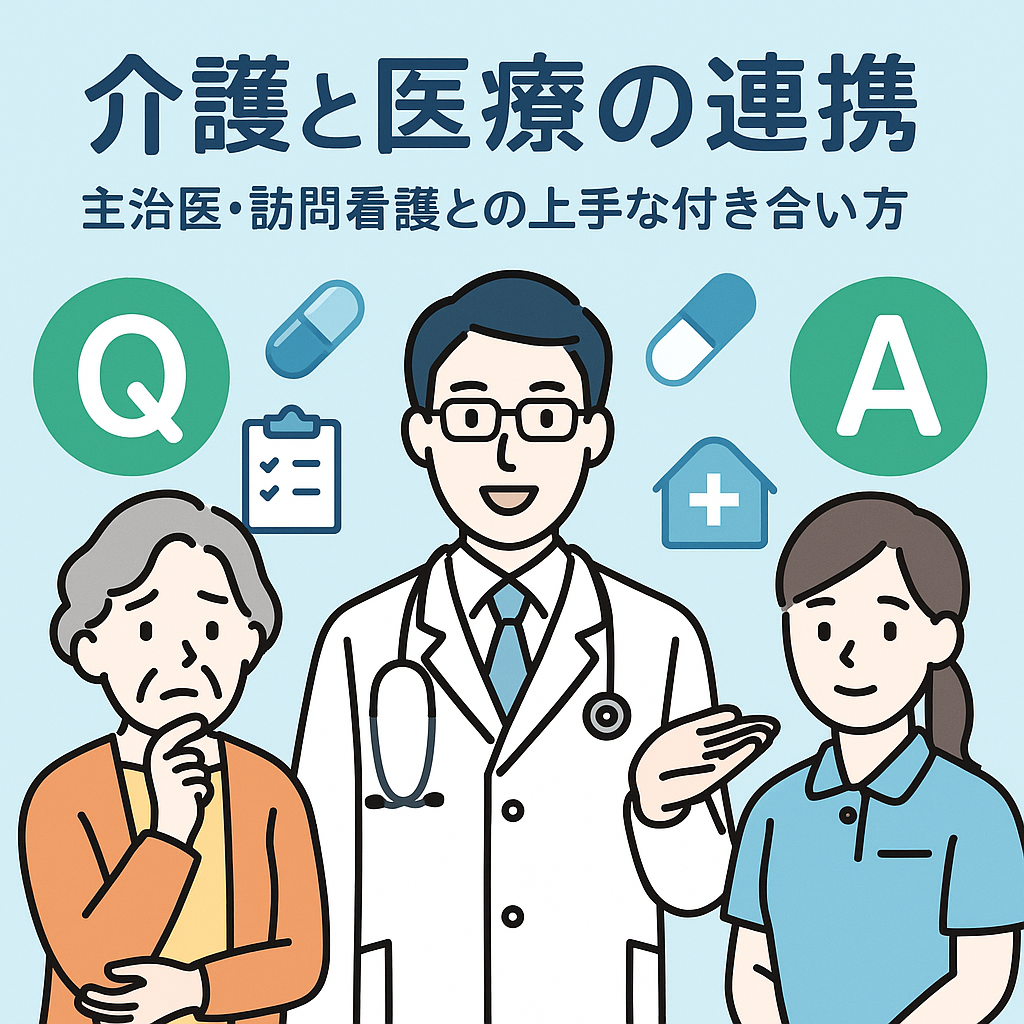
コメント