介護度が変わるとどうなる?
要介護認定は「要支援1・2」「要介護1〜5」の区分があり、介護度が変わると
- 利用できるサービスの範囲
- 1か月に使える介護保険の限度額
- 自己負担の金額
が変わります。
サービスの違い
要支援 → 要介護に変わった場合
- 介護予防中心 → 本格的な介護サービス利用が可能に
- 訪問介護の内容が拡充(掃除・調理・入浴介助など)
- 福祉用具レンタルの対象が広がる
- ショートステイや施設利用も可能
介護度が軽度 → 重度に変わった場合
- 支給限度額が上がるため、デイサービスや訪問介護を増やせる
- 要介護3以上 → 特養への入所申込みが可能
- 要介護4・5 → 介護医療院や長期入所施設が選択肢に
介護度が下がった場合
- 利用できるサービスは「介護予防」が中心
- 支給限度額は少なくなる
- ただし、自己負担が軽くなるメリットもあり
費用を抑えるための工夫
1. 制度をフル活用
- 負担限度額認定証:食費・居住費の軽減
- 高額介護サービス費:上限を超えた分は払い戻し
- 高額医療・介護合算制度:医療+介護で超過分を還付
- 医療費控除:確定申告で税金軽減
2. サービスの組み合わせを工夫
- デイサービスを週3回 → デイ2回+訪問介護に変更
- 必要な時間だけ利用し、無駄を省く
- 福祉用具レンタルを活用して自立を促進
3. 民間サービスや自治体サービスも活用
- 配食サービスや見守りサービスを組み合わせる
- 家事代行やボランティアをうまく利用する
まとめ
介護度が変わると、利用できるサービスや費用の上限が大きく変わります。
そのときは 制度を活用し、サービスを工夫して組み合わせること が費用を抑えるポイントです。
- サービス範囲と支給限度額の変化を理解する
- 制度を活用して自己負担を軽減する
- ケアマネジャーと相談し、必要なサービスを無駄なく使う
👉 介護は長期戦。知識と工夫で、安心しながら経済的にも持続可能な介護を目指しましょう。

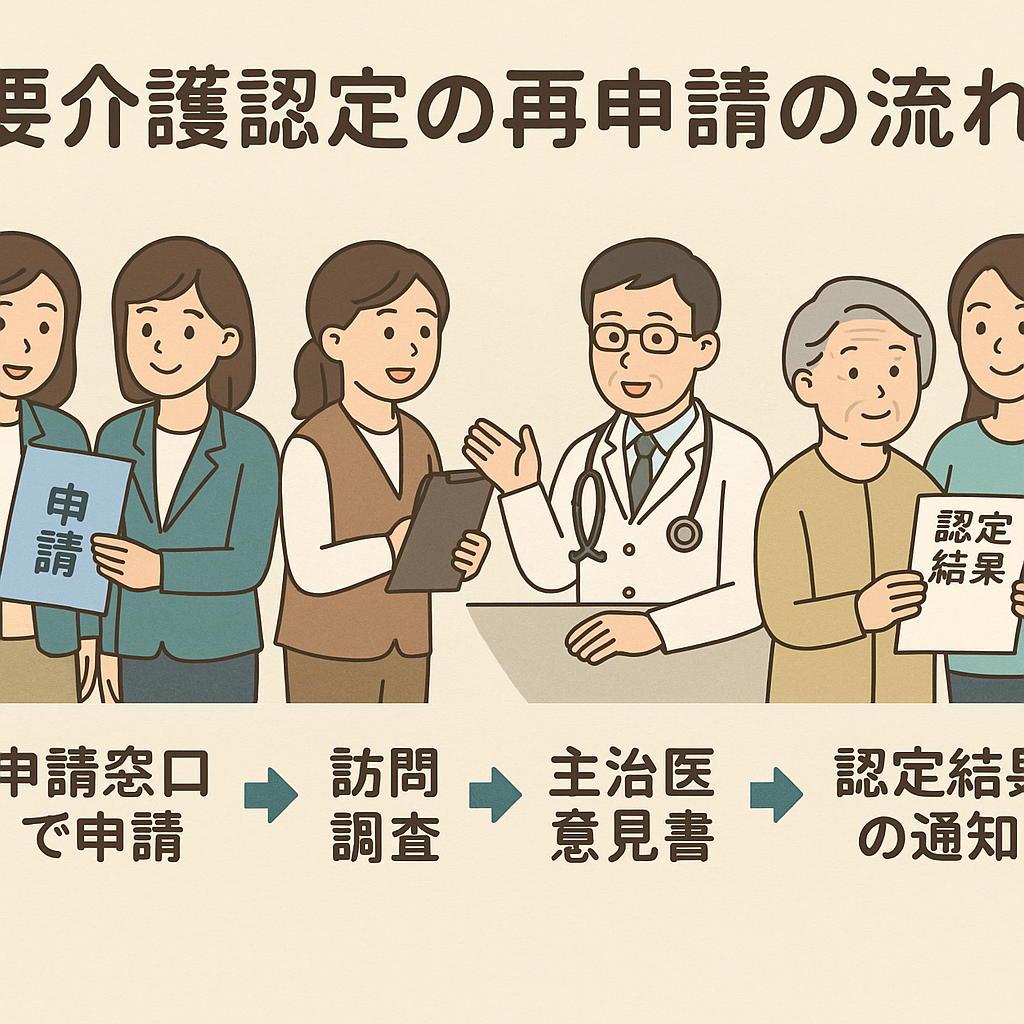

コメント